■ Happy handkerchief

諸君はこの大学の生ける伝説の正体を知っているだろうか。
昨年から黄色のハンカチを腕や足や鞄に巻くファッションが大学内で流行っているが、それは伝説の残した足跡だ。黄色のハンカチが何故ここまで大きくフィーチャーされているのか、発端はほとんどの者に知られている。しかし、それが広く知られることの意味を知るものは少ない。
では諸君に学内に広く知られる伝説の詳細と、そこに隠された真相を語ろう。
これは理学部物理学科物性物理専攻で演劇部書記、ダイソーバイト歴1年、彼女いない歴1日のやけ酒による二日酔い中の星野君と、私こと中原の出会いの話でもある。
新学期最初の講義でそれは起こった。新入生の中原は、期待と不安を胸に初登校を果たし、まだまばらにしか埋まっていない大講義室の末席に座った。友達がまだいないため、隣に誰か気さくな奴が座らないか、あるいは可愛い子が座らないかと期待していた。
始業2分前、そんな純真無垢な中原の隣にどかっとリュックを降ろした老け顔の新入生こそ星野洋平その人である。ジーンズにTシャツというラフなスタイル、おまけにサンダル。新入生の割には垢抜けを通りすぎてすさんでおり、3留していると言っても不思議はない。星野に対する第一印象はあまり良いものではなかった。
「ここ一般教養の光の科学でいいんだよね?」
隣に腰を降ろした星野が尋ねてくる。初対面でタメ口とは馴れ馴れしいとは思ったのだが、求めていた気さくな人物であるかもしれない。本当は気さくで可愛い女の子が良かったのだけど、高望みは良くない。この辺りで我慢するのが妥当だろうと中原は思った。
「あってるよ。どこの学科の人?」
「理学部物理の星野。よろしく」
「俺は法学部の中原。よろしく」
高望みをしなかったせいか、星野とは話がはずみ、低年次教養で単位修得が楽な講義や、面白そうなサークル、稼げそうなアルバイトの情報を交換した。気がつくと始業から10分過ぎていたが、教授らしき人の姿は見えない。講義室もざわついていた。
「一発目から休講か?連絡しろよって感じだな」
「一発目だから連絡しようがなかったのかもね」
「なるほどね。じゃあ俺ちょっと煙草吸ってくるよ。中原もどう?」
「俺は未成年だから」
「俺もだし。じゃあさ、教授来たらメールくれよ」
アドレスを交換したあと星野は出て行った。去り際に
「ちなみにこの赤外線も光な」
と言っていた。それくらい文系でもわかるって。そう返したが届いたかどうかわからなかった。
それから10分ほどして教授らしき白衣を着た人が入ってきたので、すぐに星野にメールを入れた。
「遅れてすみません。今日は鷹野教授が学会でいませんので代理で私が参りました。助教授の大塚です。鷹野先生からは文系の方もいるし、導入だから日常の光について何か適当に話をしてやれと言われてるだけなので、今日は雑学的な話になります。よって試験には出ません。出欠もとりませんので、自由にしてください」
そう言って大塚は講義を始めた。自由にしろとはつまり帰っていいということだろう。いかにも大学らしいそのスタイルに皆ざわついていたが、誰一人として席を発つ者はいなかった。新入生は基本的にチキンだ。
唯一席を外している星野からの返信はなかった。
大塚は30〜40台とおぼしき風貌で髪はボサボサ、丸眼鏡に口髭を蓄えており、白衣の下からのぞくジーンズはくたびれている。教授の一般的イメージに近いかもしれない。
しかし話術は巧妙で、文系の中原も興味を惹かれた。光の速さから反射、屈折、干渉、回折等の諸性質、あるいは最先端の研究や産業上の利用など、滑らかに解説した。とても適当に話してるようには思えなかった。
一番興味深かったのは電子レンジや携帯電話に用いられる電磁波も光だということと、光は波でもあり粒子でもあるということで、その話の面白さは、中原に高校一年時の文理選択を後悔させるほどだった。
講義も残り10分となった頃大塚は時計を見ながら言った。
「今日の話はだいたい終わりなんですが、何か質問ありますか?」
講義室に雁首揃えたチキン達は当然ながら誰も手を挙げない。中原も、こういう時目立つのは得策ではないと考える人種である。もしかしたら星野なんかは手を挙げるのかなとも思ったが、結局奴は講義が終わるまで帰ってこなかった。
大塚は挙手がないことを確認し
「では鷹野先生に言われていた宿題を出します」
と言った。大学にも宿題があるのかと中原を含め大半が嘆いたはずだ。
「次の講義で無地のハンカチを持って来てください。無地つまり一色の色であればいいです。持ってない方はそこに100円均一があるので調達してください」
大塚はキャンパス裏手を指さした。さすがにこれには疑問があるようでどこからか質問がとんだ。
「何に使うんですか?」
大塚は少し困った顔をしてしばらく考えてから小声で喋った。
「ネタバレになっちゃいますけど、生まれつき目の見えない人に色の概念を教えるにはどうすればいいかを考えます。例えばここに黄色のハンカチがあります。僕のですけど。このハンカチの色を目の見えない方や色盲の方に伝えるにはどうしたらいいか…と言った感じで、実際にものがあった方が考えやすいんです。詳しい事は来週鷹野先生に聞いてください」
色の概念…中原はその言葉を反芻し、講義の内容を思い返した。色と波長、加法混色と減法混色、物体の特定波長の光吸収、黒体輻射。色に関することも文字通り色々あった。
ただしその概念を光を知らぬ人に伝えるとなると、イメージしか思いつかない。赤は熱いとかピンクはエロいとか…。これはなかなか面白い講義になるかもしれない。
そんなことを考えているうちに他の受講者は講義室を出て行ってしまっていた。中原は隣の席に放置されたリュックをどうしたらよいものかと悩んだ。その時
「講義どうだった?」
と後ろから声がした。星野かと思って振り返ると、大塚だった。
「入学して初めての講義だったんですけど非常に面白かったです」
「そうですか。それはよかった。そう言っていただけると大変嬉しいです。ところで―」
大塚は蓄えた口髭を撫でながら勿体つけるように
「メール返信できなくてごめん」
と言って、そのまま髭をメリメリと剥がし、ぼさほさの髪を引っ張ってそれがかつらであることをみせた。
「何コレ?」
「おぉ星野。いいとこに来た。まだ途中なんだけど、今、次回の演劇部の定例公演のストーリー作ってたんだよ。んで星野に聞きたいことあって。適当にでっち上げようかとも思ったんだけど、なんで黄色のハンカチなんだっけ?別になんでもよかった?」
「ああ。あれはバイトで初めてハンカチを発注した時に0を1個間違えて、黄色だけが500枚きたのだよ。店長が自腹切ろとか言うから、なんとか挽回の策を練っていたというわけ。」
「悪い奴だな相変わらず。で、どう?伝説本人から見て、この舞台は成功すると思うかね?」
「中原、いろいろ言いたいことがあるのだが、2つにまとめてやろう。1つ、何故舞台の前日にふられる設定になっている。2つ、君は法学部のくせに個人情報保護法ってのを知らんのかね」
「1つ、スパイスを利かせたまで。2つ、個人名伏せればいいの?」
「名前の問題ではないのだよ。伝説ってのは言い過ぎだけど、ああいったものは真相がわかったら面白くない。そういうものなのだよ」
「もしかして例の高山さんって娘と、幻の助教授のことまだ捜してんの?」
「そゆこと。もうちょっと高山さんで遊びたい」
「相変わらず性悪だねー」
「心外だ。甚だ心外だ。乙女の夢を壊さないように必死に努めている紳士の心が、君にはわからんかね」
「どの口が紳士などとぬかしおるか」
「なんだと貴様。そこまで言うなら仕方ない。紳士たる証を見せてやる」
「ん?なんだこれは」
「塵が積もった山のように見えるが、これはサイコロの写真だ。うちのダイソーで大量に仕入れておいた」
「さてはお主、またやる気だな。いたいけな新入生を性懲りもなく騙すのか。かつての俺のように」
「まぁそんなわけで舞台化は遠慮願いたい」
「なら仕方ない。代わりに決行の日時を教えて。観戦したい」
「今のところは、火曜2限の日本国憲法概論が有力。春休みの間にゼミ生になりすまして教授の予定聞いたら、月曜から中国に出張だと言っていた。教授一人で切り盛りしてるゼミだからおそらく代理できる講師はいない」
「ぬかりないな。才能のムダ遣いしすぎだろ」
「そうそう、その件で頼みがあって来たんだけど、去年勝手に拝借したヅラと髭ってまだある?貸してもらえないかな」
「あるよ。それを舞台でも使おうとおもってたからね。面白くなってきたな」
「この性悪が!!」
「星野。君が言っちゃいかんよ」
■ 黄色くて七個のもの、なあんだ。

「っていう話なんだけど、知ってた? 黄色いハンカチ」
「いや、知らん」
「聞いたことないよ」
「私も知らない」
「春原は知ってるだろ、お前今年も教養受けてたみたいだし」
「ああ、うん、聞いたことあるかもしんない」
「まーそんなわけであるんだよ、そんな不思議な話が。幸せの黄色いハンカチ」
「幸せって単位来るだけじゃないの?」
「別に教養とか単位あまってるし」
「いいんだよ、大事なのはそういう不思議な話があるってこと。なんかほら、七不思議とか思い出さないか?」
「七不思議って小学校の?」
「私のとこは中学校もあったよ」
「俺んとこは高校だった」
「小学校でも中学校でも高専でもなんでもいいから、その七不思議だよ。大学に入ってまで七不思議があったとしたらなんかロマンじゃないか」
「いや別に」
「別に」
「別に」
「別に」
「ていうかロマンどころか存在しないじゃん、七不思議」
「そう。だから俺たち文芸部で作るんだよ、七不思議」
「またいらんことばっかり思いつくね」
「だからみんなの知ってる七不思議とかちょっと挙げていこうぜ。いいのがあったら採用するからさ」
「ちょっとちょっとまってまって。まさかここで怖い話始めるわけじゃないよね? それちょっとやめて。私怖いの苦手なんだから」
「七不思議だよ、怖くないとだめじゃん」
「なんで? 七不思議はホラーって誰が決めたの? そもそもその黄色いハンカチだって怖くないじゃん」
「そういやうちの中学の近くの野原にエロ本おじさんって妖怪がいたな。あれも七不思議だったかも」
「エロ本おじさん?」
「エロ本のリクエストを書いた紙を奉るとさ、次の週ぐらいにそのジャンルのエロ本が置いてあんの。雨水に濡れてんだけどさ。そういや悩み相談した奴もいたな」
「ぜんぜん不思議じゃないじゃん。幽霊の正体見たり近所のおっさんでしょ」
「あ、そうだ。文芸部会報を10冊買った人が好きな人と結ばれたって七不思議どうかな。ついでに会報にその話書けば信憑性アップ! 売り上げもアップ!」
「アップしねーよ」
「とにかくさ、七不思議だからホラーっていうのは旧時代の考え方だよ。ここは大学なんだし、もっと前衛的にいこうよ」
「農学部の田んぼでミステリーサークルとか」
「無理無理! 農学の吉田教授は洒落にならんってば」
「幻の西10号館の話は?」
「なにそれ」
「西10って西8と西9に囲まれてて入り口がわかんないの」
「建築的には七不思議かも」
「それ採用で。幻の西10号館のナゾを解く!」
「あと5つか」
「ねね、最後のひとつは『6つしかないのに七不思議とよぶ不思議』ってどう? 私の高校にあったんだよね、この話」
「水野ってそういう変な構造の話好きだよね」
「いいじゃん別に」
「とにかくあと4つね」
「図書館にいっつもいるバンダナのオタクっぽい人!」
「確かに不思議だけど、そういうのはやめとこうぜ」
「じゃあ物理演習棟のパソコンをいっつも使ってるチェックのシャツのオタクっぽい人!」
「それ同一人物だよねえ」
「なんかほのぼのするのがいいな。学長像に居ついた黒猫とかさ」
「お、いいね。そんな猫いるの?」
「いないよ。餌付けでもしてよ」
「いないのかよ。じゃあ春原、お前8年生まで大学いるって公言してただろ。任せた」
「マジかよ。ペットフード代だせよな」
「じゃああと3つもそれでどうだ。学長像の黒猫、体育館裏の黒猫、部室棟の黒猫、図書館の黒猫」
「適当すぎるだろ!」
「ペットフード代も掛かるしな」
「とりあえず、黄色いハンカチと西10と黒猫と6つしかない七不思議の4つは決定かな。これ今回の文芸部会報のテーマにするから、みんな残りの3つ考えてこいよ」
「あ、じゃあ会報10冊で恋愛成就もいれといて」
「残り2つね、来週までに考えといて」
「はーい」
「はーい」
「はーい」
「ところでいまさらどうでもいいんだけど、俺たちって4人しかいないよな?」
残り2つの七不思議がどうなったかはまた別の機会に語ることになると思うけど、俺たちの文芸部会報はいつもの年の1.2倍ぐらいは売れた。肝心の七不思議はあまり生徒の間で話題になることはなかったけれど、一部の教授が気に入ったりしたせいかこっそりと語り継がれているものもあるようだ。あの頃一緒に会報を作った仲間たちはもうとっくに卒業してしまって、俺は大方の予想通り今年8年生になり今でも学長の銅像の前にこっそりキャットフードを撒いている。黒猫じゃなくて白猫がいついてしまったのが、唯一の誤算かもしれない。母猫のシロは今年5匹の子どもを出産した。白猫たちに餌を与えながら単位を落としつつコンビニで働く毎日だけど、心配しなくていい、それなりに楽しくやっているよ。
■ えくすきゅーず、みー

自分の惨めな顔を見てため息をついたのは、たぶん、これで二回目だ。
小学生の時に前歯を二本同時に折ってしまったときが最初で、
あの時は顔だけじゃなくって、ため息まで「ひゅー」なんて感じで惨めだった。
今回はというと、目の下のほうに自己主張した疲れが黒と紫で広がっている。
これまで私は不健康と親しくしたことがなかったものだから、顔がこんなに酷くなるなんて思ってもいなかった。
初めまして「クマ」さん、どうぞよろしく。
もちろん、こうなったのには理由がある。
花の女子大生の私は、その花を見事に咲かせる夏休みを目の前に目下のところ試験中。
中だるみの二年目を経ての三年目は、さらにたるみを増した三段腹。
普段から真面目に代返をしていたものだから、普段から真面目な友達にすがり叱られながら徹夜の日々を送り、
本日めでたく最終日を迎えることになった。
ありがとう、優子、ありがとうグロンサン。
結果、目下のところにめでたく「クマ」さんを授かったのだ。
と、いうことにしておこう。
実際は男に振られて、悲しくて悔しくて辛くて、涙も枯れるまで泣いたせいだなんて。
「笑う強化系」、人生の友は黒霧島、身体能力テスト女子1位の私が言えるわけがない。
フランス語とフリードリンクをこれまでの人生でないくらいに消費していたわたしの携帯に
「明日の海の予定、朝9時に迎えにいくわ♪」
と、彼からの一通のメール。
はて。明日のわたしは夕方まできっちり試験。
朝一の「海洋生物論」の試験会場にドラマチックに迎えにきてくれるという意味ではないだろう。
強化系の私でもさすがに分かる。
フランス語が頭をぐるぐるかけめぐる。
ジェネラリースピーキング、イッツ、ウワキ。
海に似合うのは浮輪であって浮気ではないのに。あれ、そういえば、今のは英語だぞ。これは明日のフランス語は死んだな。死んだついでに今すぐ彼に確認してしまうか。待て待て、ちょっと落ち着こう。ここは公衆の面前だぞ。コーラでも飲んで落ち着こう。炭酸はすっきりするはずよね。あ、これウーロン茶だ、まぁいいや。
ごくごく、ひゅー。
なんて、ひとしきりあたふたしたあと、コーラをもう一杯だけ一気飲みし、パフェとドリンクバーの料金を支払い外に出た。
気づいたらもう部屋に帰り着いていて、部屋に入り今度は空気を一度だけ一気に吸い、彼に電話した。
「何かあったの?」なんてあからさまにとぼけやがったのですぐさま詰問モードへ入る。もちろん彼も送信したのを分かっているわけで、三分もしないうちに開き直った挙句、お前は五股の四番目だ、なんていう始末。
せめてもっと言い訳をしろよ、ばかやろー。
わたしはもう頭と心がぐちゃぐちゃに熱くなって、馬鹿、阿呆、死ねだのと小学生の様に罵った挙句、「もげろ!」なんて訳の分かりそうで分からない言葉を捨て台詞に電話を切った。そして、ひとしきり、泣いた。
と、いうことにしておこう。
事実はいたって普通で、相手に好きな人ができて、二年と半年にわたった遠距離恋愛が終了したというだけの話で。
電話口で「ごめん」なんて間抜けなことを言われて、間抜けに「私も頑張るよ」なんて言っただけで。
そんなことで私は泣きあかした。
今日は死んだなー、とか考えていたら、爽やかな朝の光とともにさしこんだすきま風が、ひゅーっと私のほほをなでた
■ 光の科学

やっぱり告白かしら?念願の彼氏?これで私も女になるのかしら?
中学生じゃあるまいし、うかれすぎ?
仕方ない?男の人に呼び出されたの初めてだし?
なんて考えているうちにあっという間に、約束の場所についちゃった。
同じ理系でも物理学科の建物に来たのは初めてで少し緊張してしまう。男の子ばっかり。
こんなにドキドキするものなの?
普通の人は高校生や中学生の時から、こんな素敵な体験してるの?
やっぱりうかれすぎ?
仕方ない?中学の時から漱石や鴎外が彼氏だったし?
演習室にずらりと並ぶPCの一番後ろの席に彼はいて、より正確には一番後ろの席に座っているバンダナを巻いたいかにもおたく風な人の後ろにたっていて、何やら相談をしているみたい。たぶんひそひそ話をしるんだろうけど、バンダナさんの声が大きくてところどころ単語が聞こえちゃう。
「学内からなら…造作もない」
「…これで架空人物…」
「あとは誰に…」
もしかして怪しい人?何か悪いことたくらんでる?こんな人達に関わっていいのかしら?
でも彼氏がワルってのもなんかイイ?私も大学デビュー?
それより、いまどき"ワル"なんて言う?死語?
仕方ない?初めてだし?浮かれてるし?
なんて考えているうちに、彼にみつかってしまう。別に隠れてたわけじゃないんだけど。
「こんにちは。ごめんね、休みの日に呼び出したりして」
「こんにちは。お話ってなんでしょう?」
「うん。ちょっと待ってね。歩きながら話そうか」
バンダナさんにいくつか指示を出した後、彼は紳士的にエスコートして外へ連れ出してくれた。
ノースリーブ、ショートパンツにサンダル、夏とはいえ、とても紳士には見えないけれど。
これ本当に告白?女の子と会うのにこんな恰好?
それって普通?女子高だったからわからない?
人間見た目じゃない?中身?
でも本当についていって大丈夫かしら?怪しい会話してたし?
なんて考えているうちに、図書館の裏手に着いてしまう。
よくわからない老人の像と、大きな木に囲まれた静かな場所。
避暑に最適かも。こんなところがあったのね。
「突然で申し訳ないんだけど、君に頼みがあるんだ。あ、えーと、いきなりすぎるね。自己紹介をしよう…」
そう言って彼は名乗った。私も名前だけは礼儀よく名乗ったけど、彼は既に知ってたみたい。
なんで知ってるの?
告白するなら名前くらい知ってるはず?
でもどこで手に入れたんだろう?
さっきの怪しいバンダナさんの力かしら?
いずれにしても、ストーカーの線もあるわよね?
なんて考えているうちに、彼は本題に入り始めた。
「さっそく本題に入ります…実は僕は4年生なんだけど、今年で入学してから8年目なんだよ」
「はい?」
え?8年目?今年卒業?それとも強制排除される身分かしら?
そんなことより、ストレートに入学したとしても今26?
おじさま?おやじ?人間やっぱり見た目じゃない?
26歳は考えてなかったわ。彼氏としてはあり?なし?
顔はそこそこ、ファッションは中の下…なし?
でも最初の相手としてはそれくらいの方がいいのかしら?
なんて考えているうちに、老人の像の影からみゃあみゃあと…1、2、3…6匹?
「来年から、こいつらの世話をお願いしたい」
丁度一年前、こんな経緯があって、母猫のシロとその子供、オレンジ、イエロー、グリーン、ブルー、パープルの世話をしている。
吾輩は赤松京子、彼氏はまだない
―なんてね。
■ 言いづらいんだ

「気仙沼に親友がいてね」「気仙沼がー」「大丈夫かな心配で食欲わかない…」ってもううるさい子がいる。本当に親友がいるのかはしらないし、どうでもいい。けれど被災したわけでもないのに悲劇のヒロインぶっている。気仙沼に親友がいて連絡とれなくて心配なわたし、悲劇のヒロイン、まあかわいそう。お姉ちゃんの頃には、貿易センターで働くおじさんが心配とか言ってる子がいたんだって。もちろん本当かなんて知らないし、どうでもいい。
友だちにメールを送ったけど、返ってこなかった。だけど偶然ミクシィの最終ログイン時間が1日前になってるのを見たことがある。その後ログインしてるかは知らないんだけど、わたしの友だちはたぶん大丈夫だから落ち着いたころにまたメールを送るんだ。
■ 勝手にしやがれ

不細工は女子にモテない。根暗は男子にもモテない。
故に鏡に映る男は人間にモテない。
「みゃぁ」となく黒い動物がそこに一匹だけ。
唯一の友人、「クロ」は他の野良たちの持つ特有の警戒心を持たない、言うなれば天然系の猫。
大学当初、近くの100円ショップに行って目的の品が売り切れてしまっていたことに絶望しながら部屋へと帰る途中のこと。大学に沿って続く、対向車がくるとそれなりに気分が滅入るそれなりに細い道を、黒い塊はかろやかに横切ろうとしていた。学校のフェンスの下をさらりとくぐり、柔らかにコンクリートに着地するその姿に目を奪われ僕はじっと見ていた。
日頃持て余していた寂しさからそいつの気を引いてみたくなった僕は、「みゃぁー」とそいつに声をかけた。もちろん、周囲に誰もいないのを確認して。するとそいつは、こちらを軽く見て少し僕の顔を見つめた後で、僕より高い声で「みゃぁ」と鳴いた。そして僕が来るのを待つかのようにその場でちょこんと座った。
僕はちょっと、いやとても嬉しくなり、近づいて喉をわさわさとかいてやると、「なぁぁ」とあくびとも鳴き声ともつかないような声を出した。少なくとも悪い気はしてないようで首の後ろあたりを僕のジーパンに何回かこすり付けてきて、「みゃぁ」と鳴いた。どうやらこの界隈では「みゃぁ」と鳴けば友達ができるらしい。でも、人に試すには勇気がいるし、そんな勇気は持ち合わせていないし、そんな勇気があれば「僕も新入生。よろしく。」くらいは言えると思う。
それからというもの、そいつはどうやら僕の顔を覚えてくれたようで、見かけたときに「みゃぁー」と声をかけると「みゃぁ」と返事をくれるようになり、今では向こうから声をかけてくることもある。僕が買い物袋を持っている時に限定されるけど。
「おまえのために買った訳じゃないからな」
そういって、クロのために買ってきた魚肉ソーセージを地面におくと、クロは匂いをかいだ後、しゃむしゃむと食べ始める。どうやらキャットフードは口に合わないらしく、一度買ってきたことがあったが見向きもしなかった。
「人様の食えるものなら食うなんて贅沢な奴だ。」
「むふぅ」
食べ終わったばかりのクロは、うまかったぞよ、とでも言わんばかりにため息をついた。
おいしゅうございましたか。そりゃ、結構。
そして、いつものようにクロは首を何回か僕でこすった後、大学のほうへ消えてく。
そして、いつものように僕は一人賑やかな大学構内を横目に部屋へと戻る。
そんな関係が続いていつの間にかそれが当たり前になり、こんな僕にも少しは周りの大学生が好んで使う「キズナ」なんて安っぽい言葉のようなものができたのかと思っていた三年生の夏、クロはいなくなった。いつもの脇道、いつもの夕方に出会うことがめっきりとなくなってしまって、魚肉ソーセージを食べるのは僕の役目になってしまった。そして、スーパーで買ったものをかごから袋に移し替える際にそれが入っていなかった時、とうとう僕はひとりぼっちになったなと思った。
「やぁ、佐間くん。君、猫の知り合いいない?」
物理学科の片隅の教室において、講義中にいきなり話しかけてきたのは、確か春原とかいうフリーダム系の男。間近に迫った学園祭に向けて、絶賛サークル活動中の彼が出席しているのは大変珍しいことで、僕に話しかけてくる人がこの学校において非常に少ないことを加味すると、道端で裸の一万円札を拾う位には珍しいことだ。変な奴だとは思っていたけれど、とうとう僕みたいに猫に助けを求めるほどの変り者になったのか。
「俺、春原。いたら紹介してほしいんだけど。」
「そんな猫、いないよ」
久しぶりに人と話したものだから、自分が思っている以上に低い声になった。
「そうか。猫にモテそうな顔してるなと思ってたから聞いてみたんだけど。」
いや、そんなかっこいいみたいな言い方されても。それに結局のところクロもどっかに行ってしまったし。
「今度、文芸部で会報出すから、是非買ってくれ。できれば10冊。10冊買うと彼女ができるから」
「なんだよ、それ。」
「じゃぁ、よろしく。」
猫の求人と、会報の宣伝だけをやって、春原は教室を音も立てずに出て行った。必修単位の講義を躊躇なく抜けるのは彼くらいではないかと思う。僕と言えば、量子力学をぼぅっと耳にしながら、クロは何処に行ったのかなんて、秋にふさわしいくらいにはセンチメンタルになっていた。
その日、大学の真ん中を走るいつもの帰り道が学園祭の出店の準備で賑わってしまっていたので、人通りの少ない、グランドの横の西門へと向かった。門を目の前にしたところで「みゃぁー」と懐かしい動物の声を聴いた。思わず横の茂みを見ると、僕の想像しているのとは全く対照的な、真っ白な猫がフェンスの外に向かって鳴いていた。西日にあたっているせいで体の輪郭部分はきれいな小麦色に輝いている。
「なんだよ、それ。」
久しぶりに期待なんてしたものだから、自分でも思った以上にがっかりしてしまった。春原曰く僕は猫にはモテる顔をしているようなので、試しに白猫に声をかけてみることにした。どうせ周りには誰もいないし。
「みゃぁー」
「みゃぁ」
白猫ではなかった。白猫とは別の方向から別の声がして、そちらに白猫は走って行った。なぜだか、その声がクロのもので間違いない気がした。でも、僕は走って行かなかった。彼には恋人ができて、僕と恋人と比べた結果、僕の前からいなくなったのだから。
不細工は女子にモテない。根暗は男子にもモテない。
西日の中、「みゃぁ」と鳴く大学生がそこに一人だけ。
■ 夏の水色
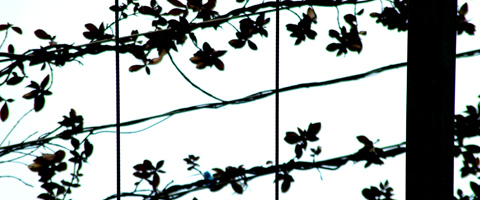
中三の頃から先輩に紹介されて援交はじめてあっというまに二十万ぐらい貯めて、なんだ人生ってぬるゲーじゃんって世の中舐めきっちゃって、それだけじゃ飽き足らず部活の後輩に斡旋してますます調子づいちゃった従姉妹の春奈が、頭悪い後輩のへまに巻き込まれて学校と親バレして自宅謹慎くらった挙句紆余曲折して夏休みの間だけうちに転がり込んできた。春奈は子どもの頃にも夏休みとかには何度か泊まりにきたことがあるけれど、あの頃からかまってちゃんで見栄っ張りで、そのくせ自分がかわいいのは自覚してる感じのめんどくさい女の子で、大きくなったらいじめっ子になるかみんなに嫌われるかのどっちだろうなーとか思ってたけど、東京はそんな二択よりは懐が広かったようで、春奈はふつーのギャルになっていた。なんでこんな田舎なのサイテーとか春奈は文句を言ってる。こんな田舎にくるのに春奈が持ってきた服は私が雑誌で見てなにこれ超かわいーやばいほしいほしいって思ってるよなブランド物ばっかりで、そっか人生ってぬるゲーなんだって思わず私も信じそうになる。ぶつぶつ言ってる春奈にそんなにあるならなんかちょうだいよって言ったら春奈はすっげー嫌がったけど、みずいろのキャミをくれた。かわいくて気に入ってるんだけど、春奈の前で着るのはなんか悔しいからって着ないでいたらいつのまにか季節はずれになっていて、結局一度も着ていない。
優太郎は私の隣の隣の家に住んでる同い年の幼なじみで、芳邦と同じ野球部に入っていたけどもう引退している。野球部はこのあいだ最後の公式戦の一回戦でコールド負けして炎天下で応援に借り出された私たちに盛大な笑いをくれた。芳邦は私が笑うと本気で怒ってたけど、優太郎は最初から無理だと思ってたみたいで、暑い中応援させてごめんとか言ってた。その顔があんまり申し訳なさそうだったから芳邦の前では大笑いした私も優太郎の前ではさすがに笑えなくて、ああ、うん、いいよ、べつにとか言ってお茶を濁して誤魔化す。優太郎とは小さい頃はよく遊んでたんだけど、小学校の中学年ぐらいになると男の子の間で女の子と遊ぶのが恥ずかしいことっていうガキっぽい暗黙の了解が自然発生するのはどの小学校でも共通のようで、面と向かってごめんもう一緒に遊ばないって言われた。当時の私にはそれがまたショックで、かといって私は泣いたりするようなタイプじゃなかったので、掃除の時間に優太郎を見かけるたびホウキで追い回してた。それまでは一緒に登校したりしてたけどそれもなくなって、それが私の淡くて薄くて味がなくて面白みもない初恋だったと言ってもまあそんなに間違いはない。私の初恋もどきはそんな風に終わっていた。
むかし春奈が泊まりにきたときにも優太郎とは一緒に遊んでいたから春奈と優太郎は知り合いだったわけだけど、夏課外を受けて暑い暑いしぬしぬはやく冷凍庫のガリガリくんたべないとしぬとか思いながら私が玄関を開けたときに春奈がアンアン言ってる声が聞こえたときにはもうなんか一瞬思考停止に陥ってそのまま脱力して座りこんだ。優太郎のっぽい靴があったし、まあそういうことなんだろうけど、家にあがる気も失せて、ガラガラと二人が気づくぐらい大きな音を立てて玄関を閉めて、そのまま理緒を呼び出してここから往復四時間ぐらい掛かるイオンまで行って、前からほしかった服とかいっぱい買ってストレス解消しようとしたんだけど、私がほしい服よりもっとかわいい服とか春奈は持ってたしきっとみじめになるんだろうなあと何も買わずにスタバでずっとしゃべってた。理緒はそういうとこ気が利くというか敏感だから、芳邦となんかあったの、とか聞いてきてくれたんだけどあの二人の話をするのも面倒くさかったから全部芳邦が悪いことにした。芳邦が最近つめたいんだよね、芳邦が最近面倒くさいんだよね、もう芳邦ぜんぜんだめ、とかとか。代わりに理緒からは憧れてる立花先輩ののろけ話を延々聞かされることになった。でもみんな立花先輩が顔だけで中身がどうしようもないほどどうしようもないことを知っている。特に女性関係。でもみんな理緒のことをかわいそうとか思ったりはしてない。本人には言いづらいから言わないんだけど、なんか理緒は自分からそういう顔とか成績とか運動神経とかそんなわかりやすいものにわざと騙されたがってる感じがすごくする。まあ言わないんだけど、絶対に。
それから数時間後にまた私は玄関の前に立ってるわけだけど、さすがに親も帰ってきてるし優太郎もいないだろうとは思うんだけどやっぱり家にあがるのに鳥肌が出て嫌悪感がむくむく湧きだして十分ぐらい立ち尽くしてたら母親が偶然出てきて、あら何してるのそろそろご飯よって言われたから夜ご飯の生姜焼きを食べた。寝る前にちょっとだけ春奈と話したけど、田舎ってそれぐらいしか暇つぶしがないじゃんとか言われて、なんか私の暇つぶしの仕方を全否定されたよな気がした。いや実際全否定されたんだと思うけどさ。
和室だったり、優太郎の家だったり、暇な夏休みをあの二人は毎日不思議な動物のように交尾して暇をつぶして過ごしていた。お盆の頃には私もだんだん慣れてきて、こんな暑い中よくやるねと思うぐらいにはなっていた。ただそれに比例して家より弟のところに行く時間が増えていた。母親が、お見舞いに春奈ちゃんも連れてってあげなって言ったけど私は断固拒否した。そもそも春奈はそんな面倒なことやりたくないだろうと思ったし、弟にそういう春奈のような生き物を近づけたくなかった。いやまあ特にそんなに大きな意味があるわけでもないんだけど、なんとなくなんだけど。病室は冷房が効いているから好きだ。正直ちょっと効きすぎてて、手とか足とか冷えて寒くなって痛くなるけど、それでも好きだ。うちの和室には冷房がないから、春奈と優太郎は汗でべとべとだったんだろうと思う。優太郎の部屋はどうだったかな、優太郎は小さな頃から自分の部屋を持ってて私はすごくそれが羨ましかった。両親に言ったらよそはよそ、うちはうちと怒られた。かと思えば母親はよく、どこどこのなになにちゃんはお勉強できるのにね、って私を非難する。理不尽すぎてあんま笑えない。そんな理不尽の塊の優太郎の部屋だけど、優太郎の部屋に冷房があったのか覚えていない。遊びに行くと優太郎のお母さんが出してくれた濃いカルピスの味だけ覚えている。喉に残る甘さと、ほんのりカルキの味。カランって氷が鳴ってた気もする。でもそれってもう十年ぐらい前なんだよね。ああそうか、私がこんなに嫌な気分になってるのはもしかしたら優太郎のことを好きだったことがあるからかもしれない。もちろん今は興味なんてないし、むしろ嫌いになったしどうでもいいんだけど。それに私には芳邦がいる。芳邦が、いる、うーん。だめだ理由としては弱い。芳邦はどうでもいいんだった。どうでもいいんだろうなあ。なんて考えてたら弟が怪訝な顔をしたので、いつもみたいにお話を聞かせてあげて、あさってはお祭りだねって話をして、そのあさってに芳邦と花火を見て、なんか流されて初キスとかしちゃってあとでうーんなんだかなあって考えたりしてたわけだけど、その間も優太郎と春奈はいつものようになにも考えることなくヤってた。
夏休みが終わると春奈は東京に帰っていった。名残惜しくもなく、春奈にもらったみずいろキャミを結局着る機会もないまま秋が来た。優太郎とはまた気まずくなって、それ以来話してもいないし、学校で見かけてもお互いなんとなく避けるようになった。母親からは、優くん東京の私大受けるみたいよって話は勝手に耳に入ってきたけど、春奈は別に優太郎のことが好きなんじゃなくてただ暇だっただけなんだから、なに勘違いしてんだよバカとか胸がもやもやして枕をぶん投げたら積み上げてた雑誌がばさっと倒れて私が欲しかった服をいっぱいもってた春奈を思い出してまたイライラして、芳邦に死ねーってメールを送って携帯の電源をぷつりと切った。私たちの秋はそんな風に過ぎたし、冬が本番を迎える頃には受験の話題が中心になっていた。そういえば来年受験の春奈は美容師の専門学校に行きたいと言っているらしい。人生ぬるゲーの春奈らしいといえば春奈らしい。優太郎はセンター試験に失敗して第一志望の東京の私大は絶望的になっていたし、かくいう私も試験中に弟のことを考えて柄にもなくセンチメンタルにひたったせいであんまりいい点じゃなかったし、芳邦とか理緒とか他の子もみんなそれなりに失敗して志望校を変えたり強行したりしていた。
私が適当に選んだ大学に受かって学校に報告しにいったときに、優太郎も偶然いたのでちょっとだけ喋った。どうせこれで最後だろうし小学生のころ好きだったんだよって言おうか一瞬だけ迷ったけど、今思えば言わなくてよかった。代わりにサイテーって言ってやった。何がサイテーなのかはよく私もわからない。けど言わずにはいられなかったのだ。まあ、真昼間からひとの家であれだけ盛っていればサイテーと言われても仕方ないよね。そのあと、優太郎は同窓会に来なかったし、成人式でも見当たらなかったし、なんとなくもう会うこともないような予感はしている。卒業して一度だけ理緒とセンター試験の話をした。みんなの進路を激変させたあんなに大変な日だったのに、ひたすら寒くて雪が降ったことぐらいしかもう覚えていないし、覚えておかなきゃいけないことなんて、きっとなかった。
■ 失踪、疾走ライダー

24通目のメール。私はまだ一度も返信をしていない。おそらくこれが最後の誘いだろう。24、5の若い男が確約されているのかさえわからない未来を想い、一年もの月日をバカの一つ覚えみたいに送り続ける誘いのメールは、行ったら行ったきり、帰りの燃料を積んでいない。こんな時代にそんなことが許されるものだろうか。少しずつ積み重ってゆく文字の重さに少しずつ沈んで身動きがとれなくなる一方で、自分の存在が彼の中に欠片でも残っていることに安堵した。
『一緒にツーリング行きませんか卒業式にバイクで迎えにあがります』
私は歳をとった。彼のおかげで延命を続けた大学生活も終わる。さすがにこれ以上は引き延ばせない。YESにしろNOにしろ何かしらの形で答えなければならない。世の中には形にする事に重きを置かなければならない場合が多々ある。有意無形のものに行き場を与えねばならない。たとえその結果として無為が与えられたとしとも。句読点すらも有さないシンプルにして最も彼自身を投影しやすい形をしたそのメールを読み直す。バイクというところに配慮の無さを感じたものの、やはり無骨な彼の性格が投影されているようで可笑しかった。愛しかった。
広い講堂に100名程の修了生。意外と博士課程も多いというのが率直な感想。3年前、生意気にも先輩である彼女の人生を否定した。「楽しいんですか?やりたいこともやらないで」そのようなことを言った覚えがある。ついでに告白した覚えもあるけど、酔いに任せて本心を言ってしまったというか。男としてあるまじきその愚行よりも、翌日酔いが醒めた状態でしっかりとふられたことよりも、そのあと彼女が就職の決まっていた大企業をけってそのまま研究室に留まったことにショックを受けた。
女で博士…最も女性として輝く時期を、華やかな都会ではなく薄汚い研究室で過ごすことになったのは、俺のせいかもしれない。そんな俺の心内を知ってか知らずか、研究室ではなにかと気を遣って面倒をみてくれた。丁度一年前の春、就職で彼女より一足先に都会に出てからは、自分の気持ちを愚直に彼女に伝えることにした。そうすることで気が晴れたし、許されるような気がした。贖罪と言えば言い過ぎかもしれないけど。
彼女を目で探す。さすがに博士ともなると地味目のスーツが多く、会場の最前列に並んだ小さな人形の様な列の中から一人を見つけ出すのは難しい。プログラムが順番に消化され、突然彼女の名前がマイクを通して呼ばれ、最前列で一人が立った。修了証書を代表で受け取るようだった。1年ぶりの彼女。ゆっくりと壇上に上がるその姿は、あまりに異様であまりに美しく、空間から切り離されたように浮いた存在だった。主席であることがそこに登る唯一の資格であり、またそれは3年間で彼女が築いたものの証であり、やはり彼女はここに残るべき人間だったのではと思う。彼女の足音が響く。表情までは見えないが、その堂々たる立ち振る舞いに畏怖すら覚えた。自分がひたすら小さな存在に思え、3年前の生意気も、ストークするかの様に送り続けたメールも、そもそも彼女の心に毛ほどの衝撃も与えられなかったのではないかと思われた。白状すると、怖かったと同時に嬉しかった。誇らしかった。あなた程の人の人生に、大きな影響を与えたのではと天狗になっていた。許しを請う一方で俺はそんなことを思って過ごしていた。
なのにあなたは。
今朝、私の修了式のためにわざわざ遠い地から駆けつけてくれた親友は、私の姿を見て
「は?なんて格好?それで式にでるの?あんた本気?最高にイカす」
と褒めてくれた。変な噂になったらどうしよう?なんてふざけたら、
「そのときは、噂に尾ひれをつけて武勇伝か七不思議にでも昇華してあげるよ」
と背中を押してくれた。おそらくこの会場のどこかで見守ってくれているはず。
学長に繋がった喋りっぱなしのマイクが切れるまでの長い時間をかけてゆっくり準備する。晴れの舞台。代表として受ける証書。それに恥じぬ業績は残したつもりだ。だからジーンズに革ジャン、そしてロングブーツで檀上に上ることだけは許してほしい。まだ足が震えている。彼は果たして見ているのか見ていないのか。振り返る勇気はまだない。
証書ではなくフルフェイスのヘルメットを手にして、彼女は式場から出てきた。道をふさぐように正面に立ち、一年ぶりの挨拶を交わす。
「お久しぶりです」
「久しぶり」
何を言うべきか、何から言うべきか迷い、言葉がでない。
「元気だった?」
という彼女の気遣いに頷くのがやっとだった。しばらくの沈黙を経てようやくきり出す。
「式観てました。格好良かったです」
「こんな格好なのに?」
そうおどけてみせる彼女は、確かに式典の類にはそぐわないやんちゃななりをしていた。完全にライダーだ。
「たしかに噂になりそうですね」
二人して笑った。彼女の服装の話題を機に一気に打ち解けてからは、肩を並べて一緒に研究してた時のように世話好きのお姉様と生意気なガキの関係に徐々に戻っていって、喫煙室では、彼女が今日のためにバイクの免許をとったこと、今日のために貯金はたいてバイクを買っていたことが明らかになり、今日のツーリングの意味を思いっきりはき違えていたことがわかったのだけど、彼女が免許持っていないことくらい知ってるわけで、ツーリングの誘いといえば、どう考えても2人乗りでという意味以外にとれないと主張すると、
「それは君の配慮が足りないだけでしょ。変なメール打つから誤解が生じるんであって、私に非をもとめるなんて論外でしょ、ふつー」
なんて悪づくもんだから、
「そんなに愛されてるとは思いませんでした」
と返すと、
「そーいうこと言うかなー。D論の合間に免許とるの結構大変だったんだから」
なんて不貞腐れてしまってたけど、それはそれで幸せだった。
「それで、どこ行くの?」
本日は晴天なり。絶好のツーリング日和ですな。
「さて、海にでもいきましょうか」
茜の夕日を背中に受け、成り行きを一から説明したら、なんだかどうでもよくなった。最高潮にあったテンションがみるみるうちに萎み、自分のどこを探しても見つからなくなってからは、話の大部分を脚色し、言葉として発した瞬間に片っ端から忘却した。悪ノリのすぎる先輩は、数多の大企業の面接官を尽くノックアウトにした持ち前の話術をもって、話を盛りに盛りまくった。だから後半は先輩がひたすら語っていた。
自分たちで盛った山があまりに険しく、進もうにも進めず、かと言って降りる術もわからなくなり身動きがとれなくなっていたところで、つとめて冷静に彼は言った。
「いい話だなぁ。でもねスピード違反はダメだからね」
「反省しています」
「あと、初心者の2人乗りもダメだからね」
「反省しています」
2回目は2人の声が揃った。
「じゃコレはおじさんからの卒業祝いだ」
受け取った違反切符は、味気ないものだったけど、先輩が
「初デート記念にしよう」
なんて嬉しそうに笑うもんだから、俺はそれを大事に持って帰って、さすがに飾ったりはしなかったけど、机の一番上の引き出しにしまって、そのまま忘れかけていた今日、延滞督促状が届いた。宛先をみると先輩の旧住所からの転送先がうちになって、今からその件について詰問するために、バイクで先輩の家までひとっ走りして来ようと思う。
■ 宇宙ネコはミャアと鳴かない

短足で禿げ上がった上司から毎日のように厭味を言われる。
付き合って3ヶ月の彼女は浮気をしてて問い詰めたら別れることになった。
大きなプロジェクトが俺の些細なミスのせいで台無しになった。
同僚からの視線は痛く、合コンに呼ばれてもそのネタで弄られるようになった。
円形脱毛症はまるで平等院鳳凰堂のよう。
そうだ、実家へ帰ろう。
ということでいそいそと辞表を提出して辞めたのが先月の末。残った有給休暇は使わせてもらえなかったけど晴れて自由の身となった。実家へ戻るまえに大学のサークルの奴らに辞めましたこれからは自由です報告をしたら急遽飲むことになった。持つべきものはなんとやら。
自分に才能がないことは自分が一番知ってたし、サークルの面子もみんなお堅い職業についた。誰一人夢を追いかけてなんかないし、そもそも夢ですらなかったのかもしれない。
文芸サークルの友だちと考えた話の中に無理やり結婚式のシーンを入れた。当時好きだった松村のウェディングドレスシーンを見たかったというそれだけのわがままな理由なんだけど、予算の都合で当然のように却下された。その松村は先々月の俺がレミングのデスマーチに陥ってる頃に社会人になってから付き合いだした外資系の金融で上手いことやってる男と結婚していた。招待状は来たけど、忙しいし複雑な気分だわで気がついたら参加は見送っていた。飲みながら写真を見せてもらった。いま手元にある。松村はやっぱり綺麗だなと思う。それにつけても、俺が予算のせいで実現できなかったひとつの夢を、もっと正しい形で実現した外資系の男である。来週には会社の寮を引き払って実家に帰ることになる。やりたいことがあるでもないけど、親は農業でもやればいいよと楽観的に捉えてくれている。才能がないことは一番知ってるけど、また何か書けたらいいなと思う。そのときにはあの頃の奴らは忙しくて、いっしょに何かすることはもうできないだろうけど、腐っていくよりはよっぽどいいかな。
宇宙ネコよ、永遠に。
■ ばっくぐらうんどてれぴん

さん、に、いち、はい終わり。
苦しかったのもこれまで、お疲れ様でした、私。
まぁ、自分でも頭のどっかでは分かっていた事だったし。ただ、それがはっきりとした感じじゃなくぼんやりとしたものだからしっかり考えることをしなかっただけ。決定的な事実がなかったから否定してただけ。それがひとつ、ぽんと目の前に差し出された今、私はそれを秤の反対側に乗せなくちゃならなくなって、もう片方の青臭い感情なんて勢いよくあの月あたりまで飛んで行ってしまった。きゅーんなんて音を立てて。私の誕生日は、彼からの電話もメールもなく終わって、背中の後ろあたりの過去の一部に溶け込んだ。
メールの数、外で会う数、交わす言葉の数、軒並み右肩下がりのここ二週間。全体の約1割にも満たないこの時間がまさか残りの9割を飲み込んでしまうとは思わなかった。1が10になって、10がじゅうっと焼け焦げて、真っ黒の消し炭が心のそこここでホクロみたいに点を作っている。
「助けて、ヒーロー!」
寂しさを紛らわすためだけにつけていたテレビから子供向けアニメが流れている。こんな時間に起きている子は正義の心が育つ前に、知らなくていい、分からなくていい暗い世の中をネットでもう知っているに決まってる。そんな、誰のためにやっているかわからないアニメは、きっと私みたいなのを慰める雑音をつくり出すためだけのものじゃないのだろうかなんて思った。
ちょうどCMに入ったところで彼からメールが届いた。今更、という怒りと、助かった安堵感が同時に襲ってきたけれど、その二つを足したところでメールを見ないなんて言う選択肢が出てこないところが私という人間だなと思う。結局のところかっこいい大人のオンナにはなれないなぁと。
『誕生日おめでと。最近あんまし時間なくてちゃんと話してなかったけどその分金はたまったので好きなもの教えて。プレゼントします。』
馬鹿じゃなかろうかと。アホじゃなかろうかと。それは事前に聞いといて当日サプライズにして贈れよと。説教したいことは山ほど頭に浮かんでくるけれど、同時にこの前一緒に出掛けた時に見かけた指輪でも買ってもらおうかとすでに考えているところが私だなとつくづく思う。顔なんかもう、緩んでニヤニヤが止まらなくて気持ち悪くなっているに違いない。
「ヒーローは遅れてやってくる!」
威勢のいい声でアニメの主人公が叫ぶ。
うるせーよ、ばーか。ヒーローなんかじゃねーし。
必死で心で毒づいたところで、メールで『指輪、この間の』と打ち込んでる私は、さっきのヒロインとなんら変わらないんだろうなぁと思った。